|
[歴 史]
干物の歴史は以外に古く、縄文時代の貝塚から魚の干物をはじめ、貝(カキ)の干物を
作る道具などが出土していることから、その頃には既に魚を乾燥させ保存する加工法が
あったのでは..、と言われています。
奈良期には正倉院文書に干物の記述が見られ、又各地から出土する木簡には租税、朝廷
への貢ぎ物として、干物が天皇に献上されたことが記録されています。
今のような干物が完成したのは江戸時代だとされています。
干物にすることで、魚の旨みや栄養がとじ込められ、栄養価が増すことを、先人たちは
知っていたのでしょうか?
現在、沼津で作られるほとんどの干物は、カチカチに乾燥させた保存食という干物では
ありません。
使われる魚(原料)の鮮度の良さを活かすため、干物としての旨みを凝縮させたまま、
風味・食感は生魚により近いものになっています。
そのため、作られてすぐに凍結される干物は、冷凍された状態のまま皆様のお手元に
届くようになっております。
(これも、ひとえにコールドチェーン網が整備されたおかげといえるでしょう。)
[旅館の朝食といえば干物]
旅先の朝、いつもは食欲のない方でも、宿での朝食に何杯もご飯をおかわりしたなんて
経験を持つ方も多いのでは?
中でも、旅館の朝食の定番、膳の中央にデンとひかえるのは魚の干物。
どうして朝食といえば干物なのでしょう?
昔懐かしい昭和の香りを感じるものだから?
それもあるかもしれませんね。
でも、干物の栄養価を考えれば旅館に限らず勤勉な(?)日本人の食卓には干物は必要
不可欠なもの。
また最近の干物は、意外と塩分が少なく、ハムなどに比べてもとても健康的!
ハムエッグにパンなど食の欧米化(欧米か!)が進むなかで、日本食の朝食のヘルシー
さは、今日世界中から熱い注目を集めているようです。
干物もいつか寿司並みに、インターナショナルな食べ物になるかも・・・。
[干物のみずみずしい弾力]
干物がふっくらとして美味しい理由のひとつに、塩分に浸すことで筋繊維が膨れること
があげられます。
繊維と繊維のすき間がなくなり、魚肉中の水分がぬけにくくなるため、みずみずしい
弾力が保たれます。
[魚は食べれば食べるほど体にいい!]
干物に向く魚はおしなべて、良質なタンパク質、カルシウム、鉄分などを多く含みます。
中でも、「タウリン」。 アミノ酸の一種で血圧の安定、動脈硬化の予防、心臓を丈夫
にするといわれ、疲労の回復や肝臓機能を高める効果が期待できます。
また優れた不飽和脂肪酸、EPA(エイコサペンタエン酸)は中性脂肪を低下させ、血
液浄化、血液の凝固を抑え、脳梗塞、心筋梗塞などを予防。
DHA(ドコサヘキサエン酸)は、脳を活性化、痴呆の予防や子供の学力向上を促すこ
とが期待できます。
また、数多く含まれるビタミンの中でも、ビタミンAは大量に含まれており、視力回復
や皮膚の成長にも効果が期待できます。
アジ干物の成分表はコチラ!→ 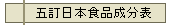
| 
